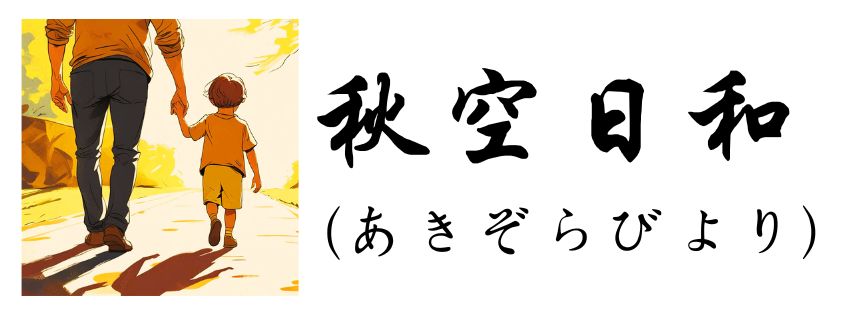【剣道ノート #03】2025年6月下旬~7月中旬:試合と稽古はつながっている

7月も終盤、夏本番を前にしたこの時期は気温も湿度も高く、竹刀を持つ手にも汗がにじみむ。
体調管理や集中力の維持が難しくなる季節。それでも地道な取り組みが実を結ぶのが剣道!まさに「継続は力なり」を感じさせられます。
小学生の取り組み:大きく、しっかり、正確に
小学生の基本稽古では、「打突の正確さ」と「姿勢」をテーマにしました。剣先の向き、間合いの取り方、足の運び方まで、すべてにおいて「丁寧に」を意識。
子どもたちは大人に比べて疲れが出やすいですが、それでも一つ一つの動作を正確に、全力で行っている姿勢が見られ、成長の跡が感じられました。
「ただ大きく振ればいい」というのではなく、「しっかり打つ」ことの難しさと大切さを、繰り返し伝えています。
8月には、級審査や木刀による剣道基本技稽古法の試合がある。
木刀剣道と竹刀剣道は繋がっていることを伝えながら、正しい構えや姿勢、打突の理合を理解、気剣体の一致など、自分も学びながら子供達にも指導していきたい。
自分の稽古:大きく、しっかり、正確に
7月12日の稽古には八段の先生が来られ、非常に印象深いご指導をいただきました。
「基本は大事、だからこそ繰り返し稽古する。私が60歳過ぎても試合に出ていた理由は、試合になると“勝ちたい”という気持ちが出て、普段の稽古と同じことができなくなる。だからこそ、稽古でも試合でも同じ動きができるようにならなければいけない」
この言葉には重みがありました。剣道は心を鍛えることが大事。心が鍛えられていないからこそ、試合と稽古の剣道が変わってしまうのだと気づかされた。
また、
「技は“出そう”と思って出すものではない。気づいた時にはもう技が出ている状態が理想。そのために、ただひたすら稽古するしかありません」
という教えも。まさに無意識に身体が動く“自然体”を目指して、継続することの大切さを改めて感じました。
地稽古での課題
地稽古では、打ちたい気持ちが強くなり過ぎて自然体になっていないこと、1本に拘っていない(残心が散漫)が、特に課題と感じた。
構えたときの足の配置や姿勢、中心の攻め方など、まだまだ研究しないといけない。
おわりに
改めて、「試合に出ること」の意味を考えさせられたこの期間。
試合とは、自分の稽古の成果を試す場所であり、自分の癖や弱点が最も顕著に現れる場所。だからこそ、恐れず、挑戦し、そこから次の稽古につなげていく――そんな積み重ねが、剣道の上達につながるのだと実感しました。
子どもも大人も、日々の稽古を丁寧に、そして意味のあるものにしていきたいと思います。