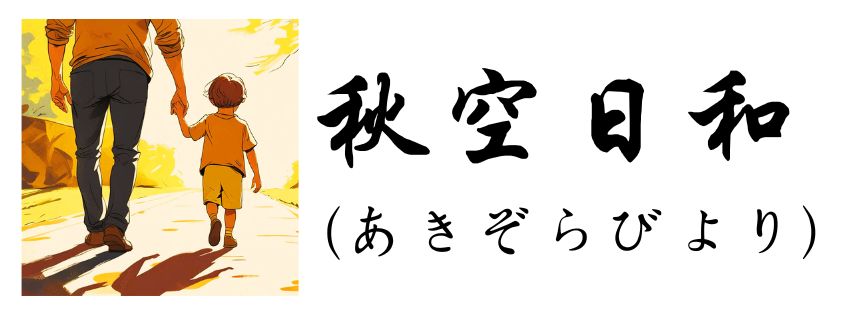【剣道ノート #04】2025年7月下旬:形の大切さを学ぶ

テレビなどでよく見るのは、剣道は防具を付けてする竹刀剣道だが、木刀を使った日本剣道形もある。
形は全日本剣道連盟のオンラインショップで購入できる日本剣道形解説書で学ぶことができるが、実践でないと学べないものも確かにある。
特に私が子供の頃は無かったが、「木刀による剣道基本技稽古法」もあり、最初にこれを学ぶことにより①構え②木刀(竹刀)の握り③姿勢④打突の機会⑤技の組み立て等の上達に役立つと思う。
以下は、日本剣道形や剣道基本技稽古法を指導される先生方が、よく言われていることの抜粋である。
尚、細かい注意点は、別の投稿にまとめるため、今回は全体的に意識することを記載する。
・(形・基)全ての動きには理由があり、それを理解することが大事。
・(形・基)呼吸も意識する。縁を切らないよう打突後から残心し構えなおすまでは息を止めておく。
・(形・基)なぜ残心は相手の眉間やのどにつけるのか。木刀は刀を模しているため、眉間やのどに付けることで相手の反撃に即対応できる。
・(形・基)ひかがみをまげない。曲げると次の技へのつながりが一歩遅れる。但し、左のかかとはつけない。
・(形・基)左手手動で動く。
・(基)1本目で、正しい姿勢・修練度が分かるので特に大事。
・(基)4本目、胴を打ったとき、しっかり下がらないと、相手が麺を振り下ろせば斬られてしまう。
・(形)色々な先生の考え、実践の仕方がある。どんな指導に対しても常に勉強する姿勢が大事。
・(基)しっかり、大きな声を出す。
・(形)迫真性のある、気迫のこもった形が人々を惹きつける。